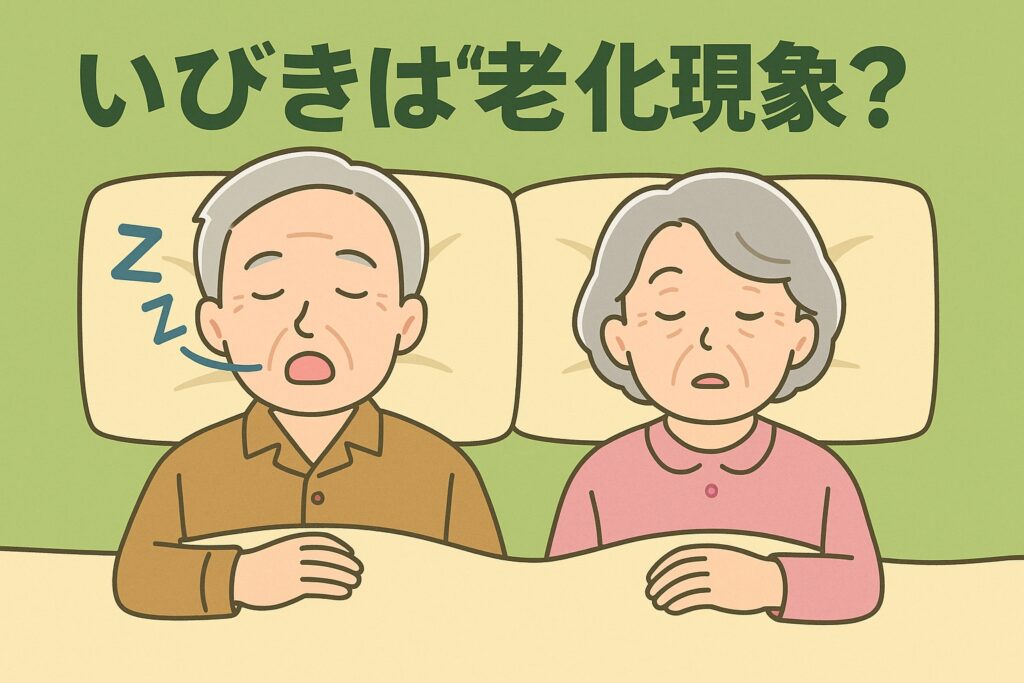
年齢とともにいびきが増えるのはなぜ?
「若い頃はいびきをかかなかったのに、年を取ってから急にひどくなった…」
そんな声は少なくありません。実は、いびきは加齢と密接な関係がある現象であり、年齢を重ねることでいびきが発生しやすくなるのは自然なことです。
この章では、加齢によってなぜいびきが起こりやすくなるのかについて、医学的な視点からわかりやすく解説します。
加齢による気道の変化が原因
いびきは、空気の通り道である「気道(上気道)」が狭くなることで起こります。
加齢に伴い、次のような変化が起きやすくなります:
-
喉や舌の筋力が衰え、気道を支える力が弱くなる
-
舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、空気の通りが悪くなる
-
軟口蓋(のどちんこ部分)がたるみやすく、振動が起こりやすくなる
これらの要因が重なることで、睡眠中に空気が通るたびに粘膜が振動し、「ゴーゴー」「ガーガー」といった典型的ないびき音が発生します。
睡眠の質と筋力の低下が影響
加齢により、睡眠そのものにも以下のような変化が現れます:
-
深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間が減少し、浅い眠りが増える
-
睡眠が不安定になり、いびきが出やすい体勢が長く続いてしまう
-
日中の活動量の低下により、筋肉全体が弱りやすくなる
特に、咽頭(のど)や横隔膜などの呼吸補助筋の筋力低下は、いびきの発生頻度や音の大きさにも影響を与えることがわかっています。
また、年齢とともに体重が増えやすくなることもあり、首回りの脂肪が増えるとさらに気道が圧迫されやすくなります。
老化によって起こる体の変化といびきの関係
加齢によるいびきの増加は、単に「年を取ったから」という一言では片づけられません。実際には、身体の複数の部位や機能に起こる変化が重なっていびきのリスクを高めているのです。ここでは、老化に伴う代表的な変化といびきとの関係性を詳しく見ていきます。
のどや舌の筋力低下
年齢とともに、咀嚼や発声に使う**舌や喉まわりの筋肉(上気道の筋群)**が衰えていきます。
これにより、睡眠中に舌が重力で喉の奥に落ち込みやすくなり、気道をふさぐ原因になります。
特に横になると重力の影響で気道が狭くなるため、仰向け寝の姿勢ではよりいびきをかきやすくなります。この現象は「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」のリスクにも直結します。
ホルモンバランスの変化
加齢によって性ホルモンの分泌が変化することも、いびきに影響を与えるとされています。
-
男性はテストステロンの低下により筋肉量全体が減少
-
女性は閉経後にエストロゲン・プロゲステロンの分泌が減少し、気道の弾力が低下
このようなホルモンの変化が、筋力・粘膜・気道の安定性に影響を及ぼし、結果としていびきや無呼吸が起こりやすくなると考えられています。
肥満や姿勢の影響も加齢と連動
中高年以降は基礎代謝が低下しやすく、内臓脂肪や首回りの脂肪が蓄積しやすい傾向にあります。
首や顎下に脂肪がつくと、気道が圧迫されて空気の通りが悪くなり、いびきの大きな原因となります。
また、加齢による**姿勢の変化(猫背・首の前傾)**も、気道を狭める要因になります。
特に寝具の高さや寝方が合っていないと、呼吸がしにくくなり、いびきがひどくなることがあります。
高齢者特有のいびき対策とは
加齢によるいびきは自然な変化の一部ではありますが、放置すると睡眠の質低下や無呼吸による健康被害につながるおそれもあります。
ここでは、特に高齢者に適した、無理なく安全に取り組めるいびき対策を紹介します。
就寝環境と姿勢を見直す
まずは毎日の睡眠環境を整えることが、いびき対策の第一歩です。
-
横向き寝を意識する(仰向けは避ける)
-
自分に合った枕の高さ・硬さに調整する
-
寝室の湿度と温度を快適に保つ
-
寝具の柔らかすぎ・硬すぎを見直す
特に「横向き寝」は気道の確保に有効で、背中にクッションやリュックを当てる工夫も有用です。
また、首が詰まりにくい枕の使用も、呼吸のしやすさに大きく影響します。
呼吸筋トレーニングの導入
のどや舌の筋力低下には、**口周りの筋トレ(オーラルエクササイズ)**が有効です。
代表的なトレーニングには以下のようなものがあります:
| トレーニング名 | 方法 |
|---|---|
| 舌上げ運動 | 舌を上あごに押し付け、5秒キープ×10回 |
| 口すぼめ呼吸 | 唇をすぼめて息をゆっくり吐く(口輪筋を鍛える) |
| ほっぺた膨らませ | 空気を入れて10秒間キープ(顔面筋を鍛える) |
これらは高齢者でも無理なくできる運動で、継続することでいびきの軽減につながる可能性があります。
医療機関でのチェックも重要
「最近いびきがひどい」「睡眠中に息が止まっていると言われた」という方は、専門医の受診をおすすめします。
特に次のような兆候がある場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。
-
日中に異常な眠気がある
-
夜間のトイレ回数が増えた
-
目覚めたときに頭痛がする
-
睡眠中に何度も目が覚める
医療機関では、自宅や病院での睡眠検査(ポリソムノグラフィー)によって呼吸状態の詳細なチェックが可能です。
必要に応じて、CPAPやマウスピースといった治療法も検討されます。
まとめと参考記事
いびきが年齢とともにひどくなるのは、多くの人に共通する現象です。
その主な原因には、喉や舌の筋力低下、ホルモンバランスの変化、睡眠姿勢の乱れや肥満など、加齢に伴う身体の変化が深く関係しています。
しかし、加齢によるいびきも正しい対策を取れば十分に軽減・改善が可能です。
特に以下のポイントが重要です:
-
横向き寝や寝具の見直しで気道の確保を意識する
-
口周りの筋肉を鍛えるトレーニングを継続する
-
必要に応じて医療機関での睡眠検査を受ける
「年だから仕方ない」とあきらめず、日々の工夫と継続がいびき対策の鍵になります。
睡眠の質を改善することで、日中の集中力や体調も大きく向上し、生活全体の質が高まるでしょう。
参考記事
-
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について|厚生労働省 e-ヘルスネット
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-035.html -
加齢と睡眠|国立精神・神経医療研究センター
https://www.ncnp.go.jp/topics/aging_sleep.html -
いびきと筋力低下の関係とは?|ナゾロジー
https://nazology.net/archives/106708 -
睡眠中のいびきと姿勢の関係性|耳鼻咽喉科情報ナビ
https://jibika-info.com/snoring-sleep-posture

